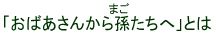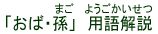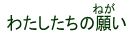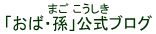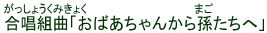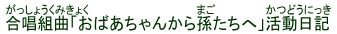「おばあさんから孫たちへ−みやぎの戦争−」公式ホームページ
「おば・孫」用語解説

まご かんまつ
このページでは、「おばあさんから孫たちへ」の巻末にまと
ちゅう かいせつ ほんぶんちゅう で むずか ようご かいせつ
めてある、「注の解説」(本文中に出てくる難しい用語の解説)
いちぶ ばっすい しょうかい
から一部を抜粋して紹介します。
ア行
イ 一億火の玉だ(いちおくひのたまだ)
いちおく こくみん てき あ せんい たか
一億の国民みんなが一つになって敵に当たろうという、戦意を高めるスローガン
オ お国のために(おくにのために)
せんそうちゅう つか ことば こじん じゆう みと いのち くに
戦争中よく使われた言葉で、個人の自由は認められず、命をも国にささげる
とうぜん
ことが当然とされた。
カ行
カ 海軍工廠(かいぐんこうしょう)
かいぐん かいじょう たたか ぐんたい
海軍―海上で戦いをおこなう軍隊。
こうしょう ふね へいき だんやく せいぞう しゅうり こうじょう
工廠―船・兵器・弾薬を製造したり、修理したりする工場。
学徒動員令(がくとどういんれい)
しょうわ ねん ねん しょうわ ねん ねん つぎつぎ くに めいれい で がくせい せいと
昭和19年(1944年)昭和20年(1945年)次々国の命令が出て、学生・生徒は、
じゅぎょう ねんかん う しょうくりょうぞうさん ぐんじゅこうじょう ろうどう おこな めいれい
授業を1年間受けずに、食糧増産、軍需工場での労働を行うよう命令されたこと。
艦載機(かんさいき)
こうくうぼかん もくてきち ちか はこ と た こうげき ていさつ
航空母艦にのせて目的地の近くまで運び、そこから飛び立って、攻撃や偵察を
ひこうき
する飛行機。
キ 玉音放送(ぎょくおんほうそう)
ねん がつ にち しょうご しょうわてんのう みずか こえ ほうそう つう せんそう はいせん
1945年8月15日正午、昭和天皇が自らの声でラジオ放送を通じ戦争が敗戦に
お つた ほうそう
終わったことを伝えた放送。
玉砕(ぎょくさい)
せんそう ま とき こうふく ほりょ じんどうてき あつか こくさいほう
戦争に負けた時には、降伏すれば捕虜として人道的に扱うべきことが国際法
さだ にほんぐん こうふく はじ きん
で定められている。しかし日本軍は、降伏を恥として禁じた。
こりつ に ば にほんぐん いっせい てきじん せ こ ぜんめつ
孤立して逃げ場をなくした日本軍は、一斉に敵陣に攻め込みながら全滅する
みち えら ぎょくさい みにく い うつく たま
道を選び、これを、「玉砕」(醜い瓦け(かわらけ)となって生きるより、美しい玉
くだ びか
となって砕けよ)と美化した。
い なんじゅうまんにん わか いのち ぎょくさい びめい
生きることのできた何十万人もの若い命が、玉砕という美名のもとで失われた。
教育勅語(きょういくちょくご)
せんぜん てんのうちゅうしん しそう きょういくほうしん しめ めいじてんのう ことば ちゅうこう しゅくん
戦前の天皇中心の思想、教育方針を示した明治天皇の言葉。忠孝(主君に
おや こうこう ちゅうしん にちじょう どうとく
つかえること、親に孝行すること)を中心とする日常の道徳をときながら、「いざ
せんそう とき くに てんのう いのち こくみん
戦争とという時には、国のため天皇のため命をささげなさい」。それこそが国民
さいこう どうとく ぎむ
として最高の道徳であり義務であるとした。
勤労動員(きんろうどういん)
せんそう へいたい あつ だんし ふ はたら ひとで た
戦争がはげしくなり、兵隊に集められる男子が増えると、働く人手が足りなく
くに こっかそうどういんほう こくみんちょうようれい ほうりつ つく がっこう じゅぎょう
なった。国は、国家総動員法や国民徴用令などの法律を作り、学校の授業を
がくせい せいと のうじょう ぐんじゅこうじょう はたら めいれい
やめさせて、学生・生徒を農場や軍需工場で働くことなどを命令したこと。
ク 空襲警報(くうしゅうけいほう)
てっき まぢか き し びょう びょう な
敵機が間近に来たことを知らせるサイレン。3秒あいだをおいて、6秒鳴らす。
かい く かえ
それを10回繰り返す。
ケ 検閲(けんえつ)
てがみ ほん えいが ないよう けんさ ひとびと しそう と し とうじ
手紙や本、映画などの内容を検査して人々の思想を取り締まった。当時は、
ぐん けいさつ きょうせいてき おこな
軍や警察などが強制的に行っていた。
コ 高角砲(こうかくほう) 高射砲(こうしゃほう)
と ひこうき つか ちゅう こがた ほう
飛んでいる飛行機をうちおとすために使った中・小型の砲
ほう かやく だんがん はっしゃ へいき
(砲ー火薬で弾丸を発射する兵器)
国民学校(こくみんがっこう)
しょうわ ねん しょうがっこう あらた しょとうか ねん こうとうか ねん ねん
昭和16年に「小学校」が改められ、初等科6年、高等科2年の8年に
えんちょう ぎむきょういく がっこう せんそう やくだ こくみん つく
延長された義務教育の学校。戦争のために役立つ国民を作ることが
きょうちょう
いっそう強調された。
御真影(ごしんえい)
てんのう こうごう しゃしん とくべつ い ことば ねんだい がっこう はいふ
天皇・皇后の写真を特別に言う言葉。1930年代すべての学校に配布され、
ほうあんでん とくべつ たてもの あんち まえ とお とき た と さいけいれい
奉安殿という特別な建物に安置し、その前を通る時は立ち止まって、最敬礼
しなければならなかった。
サ行
サ 三方交差(さんぽうこうさ)
ちじょう さんほうこう つよ ひかり だ てっき
地上の三方向から強い光を出して敵機をとらえようとすること。
シ 焼夷弾(しょういだん)
ゆし も ざいりょう つか かえん こうねつ ひと きず ころ たてもの
テルミット・油脂など燃える材料を使って、火炎や高熱で人を傷つけ殺し、建物
ばくだん たいへいようせんそう にほん おお とし ばくさん や
などをこわす爆弾。太平洋戦争では日本の多くの都市がこの爆弾で焼き
はら
払われた。
新制中学校(しんせいちゅうがっこう)
しょうわ ねん きょういくきほんほう がっこうきょういくほう せいてい がっこう せいど
昭和22年、教育基本法、学校教育法が制定され、学校の制度は6・3・3・4
せい あら ぎむきょういく だんじょきょうがく ねんせい がっこう
制となる。新たに義務教育となった男女共学の3年制の学校。
召集礼状(しょうしゅうれいじょう)
ぐんたい はい よ あつ めいれいじょう あか かみ あかがみ き
軍隊に入るため呼び集められる命令状。赤い紙なので赤紙ともいう。これが来
かなら き にちじ しじ ぶたい い
たら、必ず決められた日時に指示された部隊に行かなければならなかった。
食糧増産(しょくりょうぞうさん)
せんそう ひろ なか しょくりょうぶそく のやま かいこん すす こくみん
戦争が広がっていく中で食料不足になったため、野山の開墾を進め、国民や
がくせい せいと はたら しょくりょう しゅうかく ふ つと
学生・生徒を働かせて食料の収穫を増やすよう勤めさせた。
終戦の詔勅(しゅうせんのしょうちょく)
たいへいようせんそう おわ こくみん つ てんのう ことば
太平洋戦争を終わらせることを国民に告げた天皇の言葉。
にほん かみ くに かなら か しん こくみん はいせん こうふく う
日本は神の国だから必ず勝つと信じこまされていた国民に、敗戦と降伏を受け
い かみ てんのう ちょくせつ せつめい ひつよう
入れさせるためには、「神」である天皇の直接の説明が必要だった。
セ 千人針(せんにんばり)
せんじょう い おやこきょうだい あい ひと ぶじ ねが ひとり こ せんにん じょせい
戦場に行く親子兄弟、愛する人の無事を願って、一人1個ずつ千人の女性から
せんこ ぬ たま つく ぬの ぬの あか いと つか
千個の縫い玉を作ってもらった布のこと。さらしの布に赤い糸が使われた。
ソ 疎開(そかい)
くうしゅう さ とかい ひと ぶっし こうじょう きけん すく のうさんそん
空襲を避けるため、都会の人や物資・工場などを、危険の少ない農山村に
うつ
移すこと。
タ行
タ 大政翼賛会(たいせいよくさんかい)
しょうわ ねん ねん がつ このえないかく ほっそく くに せんそうせいさく
昭和15年(1945年)10月、近衛内閣のもとで発足。国の戦争政策をみんなで
ささ あ うえ そうりだいじん しょせいとう した となりぐみ く こ
支え合おうと、上は総理大臣から諸政党、下は隣組にいたるまでを組み込んで、
こくみん とうせい そしき
国民を統制した組織。
大東亜共栄圏(だいとうあきょうえいけん)
にほん しょくみんち ひがし
日本がアジアのかしらとなってヨーロッパ・アメリカの植民地から東アジアを
かいほう きょうりょく さか かんが あらわ ことば かっこく
解放し、協力しあって栄えていこうという考えを表す。この言葉でアジア各国を
にほん せんそう したが
日本の戦争に従わせようとした。
大東亜戦争(だいとうあせんそう)
たいへいようせんそう にほん せんそうちゅう よ だいとうあきょうえいけん つく
太平洋戦争を、日本は戦争中こう呼んでいた。大東亜共栄圏を作るための
せいせん いみ あ も つ
「聖戦」という意味合いを持たせるため使われた。
太平洋戦争(たいへいようせんそう)
だいにじせかいたいせん たいへいようちいき せんじょう にほん
第二次世界大戦のうち、アジア・太平洋地域が戦場となった、日本とアメリカ・
ちゅうごく れんごうこくぐん せんそう
イギリス・オランダ・中国などの連合国軍との戦争。
しょうわ ねん ねん がつ ひ はんとうじょうりくかいし しんじゅわんこうげき
昭和16年(1941年)12月8日のマレー半島上陸開始とハワイ真珠湾攻撃に
はじ しょうわ ねん ねん がつ ひ むじょうけんこうふく お
始まり、昭和20年(1945年)8月15日の無条件降伏で終わる。
タコ部屋(たこべや)
じゅうろうどう ひと に と こ
重労働をさせられていた人たちが、逃げられないように閉じ込められていた
へや にほんじん ちょうせんじん どれい
部屋。日本人も朝鮮人もおり、まるで奴隷のようだった。
チ 徴兵(ちょうへい)
こくみん きょうせいてき ぐんたい
国民を強制的に軍隊にかりだすこと
ト 灯火管制(とうかかんせい)
やかん くうしゅう じょうくう てっき み あ け
夜間の空襲にそなえ、上空の敵機から見つからないよう明かりを消したり、
そと ひかり まど くろ まく でんきゅう
外に光がもれないように窓には黒い幕をかけ、電球におおいをすることが
きょうせい
強制された。
隣組(となりぐみ)
しょうわ ねん がつ せいふ めいれい つく けん たんい ちいき
昭和14年8月、政府の命令で作られた、5〜10軒を一単位とする地域の
そしき しょうぼう とうかかんせい けいほう れんらく はいきゅうひん ぶんぱい しごと
組織。消防、灯火管制、警報の連絡、配給品の分配などの仕事をしたが、やが
こくみんぜんたい くに せんそうせいさく きょうりょく
て国民全体を国の戦争政策に協力させるためのものになった。
特攻隊(とっこうたい)
とくべつこうげきたい りゃく だいにじ せかいたいせんまっき ばくだん てきかん たいあ こうげき
「特別攻撃隊」の略。第二次世界大戦末期、爆弾をつんで敵艦に体当たり攻撃
ぶたい かえ はじ し かくご しゅつげき
をさせられた部隊。帰りのガソリンもなく、初めから死を覚悟で出撃させられた。
ナ行
ナ 薙刀(なぎなた)
ひろ さき なが は なが ぶき
はばが広くて先がそりかえった長い刃に、長い柄(え)をつけた武器。
ニ 日中戦争(にっちゅうせんそう)
にほん ちゅうごく しんりゃくせんそう しょうわ ねん ねん がつ か ぺきん こうがい ろこうきょう
日本の中国への侵略戦争。昭和12年(1937年)7月7日、北京の郊外の盧溝橋
にほん ちゅうごく ぐんたい ぐんじしょうとつ しょうわ ねん ねん はいせん ねんかん
で日本と中国の軍隊が軍事衝突してから、昭和20年(1945年)の敗戦まで8年間
つづ せんそう にほん いっせんまんにんいじょう ちゅうごく ひとびと ころ
続いた。この戦争で日本は、一千万人以上の中国の人々を殺し、また、たくさん
ひとびと きょうせいてき にほん れんこう こうざん きょうせいろうどう し
の人々を強制的に日本に連行し、鉱山などで強制労働させるなどはかり知れな
ひがい
い被害をあたえた。
ハ行
ハ 配給(はいきゅう)
ぶっし た くに かんり とうろく かてい ぶっし くば
物資が足りなくなったので、国が管理して、登録した家庭に物資を配ること。
しょうわ ねん こめ はじ あと さとう しょうゆ せっけん さけ
昭和十六年の米に始まり、後には砂糖、マッチ、みそ、醤油、石鹸、酒、たばこ、
かし はじ にちじょうせいかつひん はいきゅう じゆう か
菓子を始め、いっさいの日常生活品が配給となり自由に買えなくなった。
八紘一宇(はっこういちう)
しほうはっぽう ひろ せかい にほん てんのう かぞく なかよ
「四方八方に広がる世界が、日本の天皇のもとで一つの家族のように仲良く
く にほん せかいしはい たた ことば
暮らすように」という、日本の世界支配を讃えた言葉。
ヒ 引き揚げ(ひきあげ)
にほん しはい ちいき せいかつ ひとびと せんそう お あとこくがい
日本が支配していた地域で生活していた人々が、戦争が終わった後国外から
にほん かえ
日本に帰ってくること。
非国民(ひこくみん)
こくみん ぎむ まも もの しょうわ ねんころ すべ めん せんそう きょうりょく
国民としての義務を守らない者。昭和17年頃から全ての面で戦争への協力が
くに もと すこ はん おも もの ひこくみん
国から求められた。そして、これに少しでも反すると思われる者は「非国民」
ひなん
として非難された。
火たたき(ひたたき)
せんじちゅう しょういだん おと とき ひ け どうぐ
戦時中、焼夷弾を落とされた時に火を消す道具。
B29(びーにじゅうく)
ぐん おおがた ばくげきき とう しょとう
アメリカ軍の大型の爆撃機。サイパン・テニアン・グアム島などマリアナ諸島の
きち にほんぜんどくうしゅう しゅうせん く かえ こうそく そうび すぐ ため
基地から日本全土空襲を終戦まで繰り返したが、高速で装備も優れていた為、
にほんぐん せんとうき
日本軍の戦闘機はたちうちできなかった。
ブ 武運長久(ぶうんちょうきゅう)
ぶうん せんじょう ぐんじん うんめい
武運→戦場での軍人としての運命
ちょうきゅう なが ひさ
長久→長く久しい
ぶし ぐんじん たたか なか うん いのちなが かえ ねが
武士や軍人が戦いの中で運よく命長らえて帰ってこられるよう願うこと。
武士道(ぶしどう)
ぶし あいだ おも どうとく ちゅうぎしん めいよ いのち たいせつ かんが
武士の間で重んじられた道徳。忠義心や名誉を命より大切なものと考えた。
ホ 奉安殿(ほうあんでん)
ごしんえい てんのう こうごう しゃしん ごしんえい らん さんしょう い そうこ
「御真影」という天皇・皇后の写真(御真影の欄を参照)を入れるための倉庫
かさい こうしゃ はな ばしょ おお いしつく た
で、火災にあわないよう校舎から離れた場所に、多くは石造りで建てられた。
こうち なか しんせい ばしょ まえ とお とき さいけいれい
校地の中でもっとも神聖な場所とされていて、その前を通る時は、「最敬礼」を
ぎむ づ
義務付けられていた。
防空頭巾(ぼうくうずきん)
ぬの めん い つく くうしゅう とき あたま ひがい ふせ
布に綿を入れて作り、空襲の時は、頭にかぶって被害を防いだもの
防空壕(ぼうくうごう)
くうしゅう とき ひなん にわ いえ ゆかした じめん ほ つく あな
空襲があった時避難するため、庭や、家の床下の地面を掘って作った穴。
いえ ほ
どこの家でも掘らせられた。
マ行
マ 満州事変(まんしゅうじへん)
しょうわ ねん ねん がつ ひ ちゅうごくとうほくぶ ほうてん いま しんよう ほっぽう
昭和6年(1931年)9月18日、中国東北部の奉天(今の瀋陽)の北方の柳条湖
にほん かんとうぐん みなみまんしゅうてつどう ばくは ちゅうごくぐん おこな
(りゅうじょうこ)で日本の関東軍は南満州鉄道を爆破、これを中国軍が行ったこ
りゆう ちゅうごくとうほくぶ しんりゃく せんりょう まんしゅうじへん よ
とにして、それを理由に中国東北部を侵略、占領した。これを満州事変と呼んだ。
ム 無条件降伏(むじょうけんこうふく)
せんそうちゅう ぐんたい なん じょうけん あいてこく こうふく
戦争中の軍隊が何の条件もつけずに相手国に降伏すること。
ヤ行
ヤ 靖国神社(やすくにじんじゃ)
てんのう せんし ひと かみ とうきょう くだん じんじゃ
天皇のために戦死した人のうちで、神としてまつる東京の九段にある神社。
じんじゃ なか とくべつ あつか りくかいぐんしょう かんり
神社の中でも特別なものとして扱われ、陸海軍省が管理した。
闇(ヤミ)
やみいち やみぶっし とうせい て い ほうほう
闇市、闇物資のように、統制されていないルールでこっそり手に入れる方法で
きんし
禁止されていた。
ラ行
リ 陸軍第二師団(りくぐんだいにしだん)
にほん ぐんたい りくぐん なか せんだい あおばやま
日本の軍隊(陸軍)を二十二のグループにわけたが、その中で、仙台の青葉山
しれいぶ だいにしだん
に司令部のあったものを第二師団という。
慮溝橋(ろこうきょう)
ぺきんこうがい はし はし にほんぐん えんしゅうちゅう ひとり へい ゆくえふめい
北京郊外の橋。この橋のたもとで日本軍が演習中、一人の兵の行方不明を
りゆう ちゅうごくぐん こうげき へい み ていせんきょうてい このえ
理由に中国軍を攻撃。その兵が見つかり、停戦協定をとりつけながら、近衛
ないかく きゅうきょ おうえんぶたい ふ ぶりょくちんあつ せいめい はっぴょう ちゅうごく こう
内閣は急遽応援部隊を増やし、武力鎮圧の声明を発表。中国はこれに抗して
たたか た あ にっちゅうかん ぜんめんてき せんそう
戦いに立ち上がり、日中間の全面的な戦争となる。